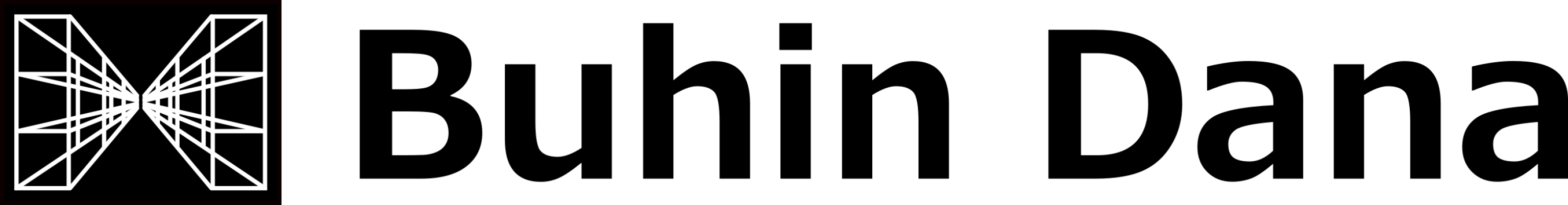絶縁抵抗計とは|BuhinDana
絶縁抵抗計は、電気設備の安全を確保するために不可欠な測定器です。電気設備の絶縁状態を数値で評価するための絶縁抵抗測定に使用され、現場では「メガー」とも呼ばれています。絶縁抵抗とは、電流が外部に漏れ出さないようにするための抵抗値であり、その意味は電気を断ち切る能力を指します。絶縁抵抗計は、この絶縁状態が良好であるかを確認するために用いられます。



絶縁抵抗計(メガー)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器ほか豊富なメーカーの絶縁抵抗計(メガー)をお取り扱いしています。絶縁抵抗計(メガー)のご用命はぜひ BuhinDana まで。
絶縁抵抗測定の概要
絶縁抵抗測定は、電気を使用する設備の安全性を確認するために行われる重要な作業です。この測定の主な目的は、電気が設備の外に漏れ出さない能力、すなわち絶縁性を数値で把握することにあります。
絶縁抵抗測定の目的
絶縁抵抗測定の目的は、電気設備における漏電のリスクを未然に防ぐことにあります。絶縁体が劣化すると、電流が本来の経路から外れて漏れ出す漏電が発生し、感電事故や火災の原因となる可能性があります。また、漏電は電気の無駄遣いにもつながり、効率的な電力供給を妨げます。絶縁抵抗測定を行うことで、このようなトラブルの兆候を早期に発見し、設備保全や修理・交換時期の判断に役立てることが可能です。定期的な測定によって、施設全体の安全性も確保できます。
絶縁抵抗とは何か
絶縁抵抗とは、電気の流れにくさを数値で表したものです。電流が電線の外部へ漏れ出ることを防ぐ「絶縁」の性能を評価するための抵抗値を指し、単位はΩ(オーム)またはその100万倍であるMΩ(メガオーム)で表されます。絶縁抵抗計は、内部で直流電圧を発生させ、被測定物にその電圧を印加し、流れる微小な電流を測定することで絶縁抵抗値を計算する仕組みです。オームの法則(抵抗=電圧÷電流)に基づいて絶縁抵抗を求めるため、絶縁抵抗値が高いほど、電気の漏れが少ない良好な状態であると判断できます。
絶縁抵抗測定の基準
絶縁抵抗測定の基準は、電気設備に関する技術基準を定める省令によって規定されています。この省令では、電路の使用電圧区分に応じて、それぞれ満たすべき絶縁抵抗値が定められています。例えば、300V以下の対地電圧150V以下の回路では0.1MΩ以上、その他の300V以下の回路では0.2MΩ以上、300Vを超える回路では0.4MΩ以上が一般的な基準値です。これらの数値は最低限の基準であり、新設時の設備では1MΩ以上が望ましいとされています。測定結果がこれらの規定値を下回る場合、絶縁不良と判断され、感電や火災のリスクが高まるため、適切な処置が必要です。



絶縁抵抗計(メガー)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器ほか豊富なメーカーの絶縁抵抗計(メガー)をお取り扱いしています。絶縁抵抗計(メガー)のご用命はぜひ BuhinDana まで。
絶縁抵抗計について
絶縁抵抗計は、電気設備の絶縁状態を測定するために不可欠な機器です。様々な種類があり、その選び方には測定対象や用途に応じた考慮が必要です。
絶縁抵抗計の役割
絶縁抵抗計は、電気設備の絶縁性能を測定し、漏電や感電、火災などの電気事故を未然に防ぐ上で重要な役割を担う機器です。この機器を使うことで、電気が外部に漏れ出ていないか、絶縁体が劣化していないかといった電気の安全性を客観的に評価できます。絶縁抵抗計の使い方は、基本的に測定対象に高電圧を印加し、その際に流れる微小な電流から絶縁抵抗値を算出するというものです。現場での点検や工事完了後の検査において、電気設備の安全基準が満たされているかを確認するために頻繁に用いられる機器であり、その使用方法を正確に理解することは、電気工事士や保守・管理に携わる実務者にとって極めて重要です。
絶縁抵抗計の測定原理
絶縁抵抗計は、「メガー」とも呼ばれ、測定対象に直流電圧を印加し、その際に流れる電流値から抵抗値を計算する仕組みです。この測定方法の基本原理はオームの法則(抵抗=電圧÷電流)に基づいており、これにより電気の漏れにくさ、つまり絶縁状態を数値で評価します。絶縁抵抗が高いほど、電流の漏れが少ない、良好な絶縁状態であると判断されます。測定器内部には直流電源、電流計、電流保護素子、測定開始スイッチが組み込まれており、本体のライン(LINE)端子とアース(EARTH)端子を被測定物に接続し、スイッチをオンにすることで測定が可能です。アナログ式の絶縁抵抗計では、針の振れ具合から絶縁の良否を判断することが多く、針が初期位置の「∞」に近いほど絶縁状態が良好で、0に近づくほど絶縁不良の可能性が高いことを示します。
絶縁抵抗計の種類
絶縁抵抗計には様々な種類があり、用途や機能に応じて選択できます。大きく分けると、アナログ式とデジタル式、低圧用と高圧用、単レンジ式と多レンジ式といった形式があります。アナログ式は針の動きで直感的に抵抗値の変化を確認できる特徴があり、特に絶縁の良否を素早く判断したい場合に用いられます。一方、デジタル式は正確な数値をディスプレイに表示するため、読み取り間違いが少なく、暗い場所での作業にも適しています。小型でハンディサイズのものが多く、持ち運びにも便利です。また、測定電圧によって低圧用(1000Vまで)と高圧用(1000Vを超えるもの)に分類され、測定対象の電圧レベルに合わせて適切な機器を選ぶ必要があります。さらに、太陽光発電設備の測定に対応した「活線メガー」と呼ばれる特殊なタイプも存在し、こちらは直流活線部の測定が可能で、オートディスチャージ機能やデータ記録機能などを備えている機種もあります。絶縁抵抗計の選び方には、測定範囲、精度、表示形式、そして測定開始方法(レバー式かボタン式か)やその他の付加機能なども考慮に入れることが重要です。
アナログ式とデジタル式の違い
絶縁抵抗計にはアナログ式とデジタル式の2つの主要な形式があり、それぞれ異なる特徴を持っています。アナログ式は、メーターの針の動きで絶縁抵抗値を確認するタイプで、初期位置では「∞(無限大)」を指し、抵抗値が低いほど針が「0」に近づくことで絶縁状態の良否を直感的に判断できます。針の振れ具合から絶縁の傾向を視覚的に捉えやすいため、熟練者にとっては効率的な検査が可能です。一方、デジタル式は測定値を数値で表示するため、読み間違いが少なく、誰にでも正確な抵抗値を読み取れる点が大きなメリットです。暗い場所でも使用できるようディスプレイにLED照明を採用した機種も多く、より精密な測定値を求める場合に適しています。現代では多くの計測器がデジタル化されている中で、絶縁抵抗計は依然としてアナログ式のシェアが高い傾向にありますが、デジタル式も徐々に普及してきています。最終的な選択は、測定の目的や作業者の慣れ、視認性の好みによって異なります。
定格測定電圧の選択
絶縁抵抗計を使用する際には、測定対象となる回路や機器の電圧に適した定格測定電圧(レンジ)を選択することが非常に重要です。定格測定電圧とは、絶縁抵抗計が測定対象に印加する電圧のことであり、一般的な絶縁抵抗計は複数の定格測定電圧に対応する多レンジ式が多く、ダイヤル操作で切り替えが可能です。例えば、100V系の低電圧配電路や機器の維持・管理には100V/125V、200V系の低圧電路には250V、600V以下の低電圧配電路や機器の維持・管理、竣工検査には500Vが用いられます。600Vを超える回路や機器の絶縁測定には1000Vが選択されます。また、太陽電池アレイの絶縁測定には、P-N端子間を短絡する方法と短絡しない方法でそれぞれ適切な電圧が指定されています。測定電圧が高すぎると、測定対象の設備に損傷を与える可能性があるため、対象設備の定格電圧や種類を事前に確認し、取扱説明書に従って適切な電圧レンジを設定することが不可欠です。多くの機種が50V、100V、125V、250V、500V、1000Vなどのレンジを備えています。
絶縁抵抗計による電圧測定
絶縁抵抗計は、その本来の機能である絶縁抵抗測定に加えて、電圧測定機能も備えている機種があります。これは、測定対象回路に電圧がかかっていないか、つまり停電状態であることを確認するために非常に重要な機能です。絶縁抵抗測定は高電圧を印加するため、通電状態の回路で測定を行うと、感電や機器の損傷につながる危険性があります。そのため、測定前に必ず検電器や絶縁抵抗計の電圧測定機能を用いて、回路が無電圧であることを確認する手順が不可欠です。活線警告機能として、危険な電圧の発生を知らせる赤色LEDを搭載している絶縁抵抗計も存在します。電圧測定機能は、電気設備の安全な点検作業をサポートする上で、補助的ながらも重要な役割を果たします。



絶縁抵抗計(メガー)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器ほか豊富なメーカーの絶縁抵抗計(メガー)をお取り扱いしています。絶縁抵抗計(メガー)のご用命はぜひ BuhinDana まで。
絶縁抵抗測定の実施方法
絶縁抵抗測定は、電気設備の安全性を確保するために重要な作業です。正確な測定結果を得るためには、適切な手順と注意点を理解し、実践することが不可欠です。ここでは、絶縁抵抗測定の具体的な実施方法について解説します。
測定前の準備
絶縁抵抗測定を行う前には、安全かつ正確な測定のためにいくつかの重要な準備が必要です。まず、測定対象となる回路の電源を確実に遮断し、停電状態であることを確認します。検電器を使用して無電圧であることを確認することも重要です。次に、感電などの事故を防ぐため、必ず絶縁手袋や保護メガネなどの適切な保護具を着用します。測定に使用する絶縁抵抗計のリード線に断線がないか、ワニ口クリップの接続状態に問題がないかなど、機器の点検も行います。必要に応じて、測定箇所のケーブルや配線を整理し、測定作業がスムーズに行える環境を整えることも大切です。また、測定対象に接続されている負荷(電気機器)は、線間絶縁抵抗を測定する際は全て取り外す必要があります。絶縁抵抗計の取扱説明書を事前に確認し、使用する機種の特性や安全上の注意点を把握しておくことも、測定を安全に進める上で非常に重要です。
測定の手順
絶縁抵抗の測り方として、まず測定対象となる回路の電源をオフにし、検電器で無電圧であることを確認します。これは、通電状態での測定は感電や機器損傷のリスクがあるため、絶対に避けるべきです。測定に入る前に、絶縁抵抗計の始業前点検と、リード線をショートさせて「0MΩ」を示すかどうかのゼロ確認を行い、機器が正常に動作することを確認します。次に、絶縁抵抗計のLINE(ライン)端子側のプローブを測定対象の電路に、EARTH(アース)端子側のワニ口クリップを接地端子または盤の金属筐体などの接地されている箇所にしっかりと接続します。対地間絶縁抵抗を測定する際は、負荷は使用状態にしますが、線間絶縁抵抗を測定する際は全ての負荷を取り外します。接続後、測定器の測定ボタン(TESTボタン)を押し、ディスプレイに表示される絶縁抵抗値を読み取ります。アナログ式の場合は、針の振れ具合で絶縁の良否を判断し、デジタル式の場合は数値を確認します。測定後は、回路に残留する電荷を放電させることが非常に重要です。静電容量の大きい回路では特に電荷が溜まりやすいため、感電のリスクを避けるために必ず放電作業を行いましょう。多くの携帯型絶縁抵抗計には放電回路や自動放電機能が備わっているため、取扱説明書に従って適切に放電します。放電を確認したら、測定リードを被測定物から外し、測定作業を終了します。
測定箇所の確認
絶縁抵抗測定を行う際には、測定箇所の正確な確認が非常に重要です。測定は、電路の「電線相互間」と「電路と大地との間(対地間)」の大きく2種類に分けて実施します。対地間絶縁抵抗の測定では、絶縁抵抗計のアース(EARTH)端子を被測定回路の接地端子に接続し、ライン(LINE)端子を測定対象の電線に当てて測定します。この際、ワニ口クリップが正しく接地されているかを導通チェックで毎回確認する習慣をつけることが推奨されます。線間絶縁抵抗の測定では、各相間の絶縁状態を確認します。単相2線ではL-N間、単相3線ではL1-N間、L2-N間、L1-L2間、三相3線ではR-S間、S-T間、T-R間、三相4線ではR-S間、S-T間、T-R間、R-N間、S-N間、T-N間など、接地を除く全ての相の組み合わせを測定します。線間絶縁抵抗測定においては、アース端子とライン端子の区別は不要で、プローブの接続を入れ替えても問題ありません。竣工検査では全ての回路の線間と対地間絶縁抵抗を測定しますが、定期検査では漏電確認のために対地間絶縁抵抗のみを測定することが一般的です。測定を行うブレーカーや分電盤の回路番号、回路電圧などを事前に確認し、測定結果を正確に記録するための準備も怠らないようにしましょう。
測定後の処置
絶縁抵抗測定が終了した後は、必ず測定対象の回路に溜まった残留電荷を放電させる必要があります。絶縁抵抗計は測定のために高電圧を印加するため、特に静電容量が大きい機器や長い電路では、測定後も電気が蓄積されている可能性があります。この残留電荷を放置すると、感電事故の原因となるため非常に危険です。多くの絶縁抵抗計には、測定後に自動的に電荷を放電する機能(オートディスチャージ機能)が搭載されています。自動放電機能付きの機種を使用する場合は、取扱説明書に従って放電作業を行いましょう。自動放電機能がない場合は、測定リードを接続した状態で短絡させるなどして、確実に放電させる必要があります。放電が確認できたら、測定コードを被測定物から外し、測定作業を完了します。これらの測定後の処置を怠らないことで、安全な作業環境を維持し、電気事故のリスクを低減することができます。



絶縁抵抗計(メガー)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器ほか豊富なメーカーの絶縁抵抗計(メガー)をお取り扱いしています。絶縁抵抗計(メガー)のご用命はぜひ BuhinDana まで。
絶縁抵抗測定の注意点
絶縁抵抗測定は電気設備の安全確保に不可欠な作業ですが、高電圧を取り扱うため、いくつかの重要な注意点があります。これらの点に留意することで、作業の安全性が確保され、正確な測定結果を得ることが可能になります。
測定時の危険性
絶縁抵抗測定は、電気設備に高電圧を印加して行うため、感電のリスクが常に伴います。測定中は回路に高い直流電圧がかかるため、万が一回路に触れてしまうと感電する恐れがあり、非常に危険です。このため、測定作業を行う前には、必ず測定対象の回路の電源を遮断し、検電器などを用いて無電圧であることを確認することが必須です。電源が入ったままの通電状態で測定を行うと、感電の危険だけでなく、測定結果が不正確になったり、最悪の場合、測定器や機器の内部にある電子部品が破壊されたりする可能性もあります。また、測定前には必ず絶縁手袋や保護メガネなどの適切な保護具を着用し、素手での作業は厳禁です。測定中は、周囲の作業者にも測定中であることを周知し、不用意に回路に近づいたり触れたりしないよう人払いを行うことも重要です。測定ボタンをロックした状態で放置すると、誤って不要な箇所にテストリードが触れてしまい、機器の故障や感電などのリスクがあるため、測定時以外は必ずロック機構を解除し、安全な状態にしておくように心掛けましょう。インバータ回路の場合、絶縁抵抗測定は半導体素子を破壊する危険があるため、実施を避けるべきです。
測定値の確認
絶縁抵抗測定を行った後は、測定値の確認と判定が重要です。測定値は電気設備技術基準に定められた規定値と比較し、合否を判断します。例えば、回路の使用電圧によって基準値は異なり、300V以下の対地電圧150V以下の回路では0.1MΩ以上、その他の300V以下の回路では0.2MΩ以上、300Vを超える回路では0.4MΩ以上が一般的な判定基準です。新設時の設備では、1MΩ以上が望ましいとされています。測定器には有効測定範囲が設定されており、この範囲内で得られた数値の精度が保証されます。有効測定範囲外の数値は精度が保証されないため、測定器の仕様を確認し、適切なレンジで測定することが重要です。また、デジタル式の絶縁抵抗計は数値で表示されるため読み間違えのリスクは少ないですが、アナログ式の場合は目盛りの読み取りに注意が必要です。測定した数値が基準値を下回る場合は、絶縁不良と判断され、感電や火災のリスクがあるため、早急な点検や修理が必要となります。測定結果を正確に記録し、経時変化を追うことで、設備の劣化傾向を把握し、予防保全に役立てることも可能です。
測定環境の影響
絶縁抵抗測定の際には、測定環境が結果に影響を与える可能性があるため、いくつかの注意点があります。特に、温度や湿度は絶縁抵抗値に大きく影響を及ぼす要因です。一般的に、湿気が高い環境では絶縁抵抗値が低下する傾向にあります。そのため、雨天時や高湿度の条件下での測定は、実際の絶縁状態よりも低い値を示すことがあるため、注意が必要です。測定環境の温度変化も同様に影響を与えるため、できる限り安定した環境で測定することが望ましいです。また、測定対象物の表面に汚れや水分が付着している場合も、正確な絶縁抵抗値を測定できない可能性があります。測定前には、対象物の表面を清掃し、乾燥させるなど、適切な準備を行うことが重要です。これらの環境要因を考慮せずに測定を行うと、誤った判定を下してしまう恐れがあるため、測定時の環境条件も記録し、結果を評価する際の参考にすると良いでしょう。



絶縁抵抗計(メガー)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器ほか豊富なメーカーの絶縁抵抗計(メガー)をお取り扱いしています。絶縁抵抗計(メガー)のご用命はぜひ BuhinDana まで。