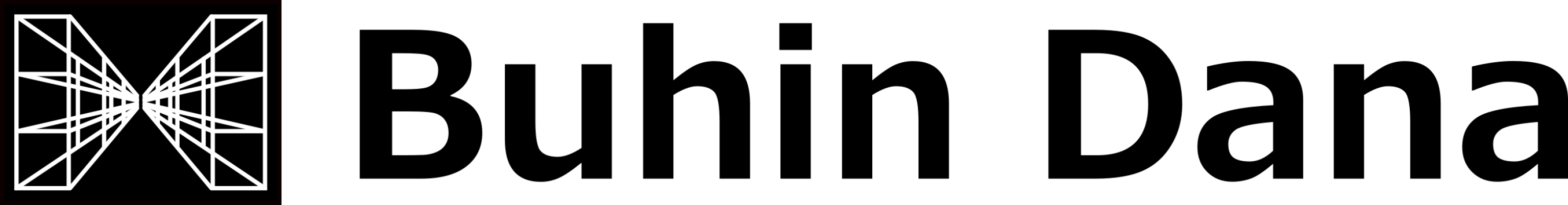接地抵抗計とは|BuhinDana
電気設備において、感電防止や機器の保護、そして回路の安定稼働のために不可欠なのが「接地」です。接地が適切に行われているかを確認する際に用いられるのが接地抵抗計であり、電気工事士や設備保全担当者など、電気に携わる専門家にとって欠かせない測定器となります。本記事では、接地抵抗計の基礎知識から測定原理、具体的な測定方法、さらには適切な接地抵抗計の選び方まで、実務に役立つ専門的な情報を提供いたします。



接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器
接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気
接地とは
接地とは、電気設備や電路、あるいは電子機器の筐体などを電気的に大地と接続することです。別名「アース」とも呼ばれ、英語の「Earth」が語源となっています。接地は、電気を安全に利用するために非常に重要な役割を担っており、その目的は多岐にわたります。
接地の目的と重要性
接地は、電気の安全性を確保する上で極めて重要です。主な目的は、感電事故や火災の防止、電気機器の保護、そして回路の安定動作を確保することです。例えば、電気機器の絶縁が劣化して漏電が発生した場合、接地が施されていれば、漏れた電流が大地へ安全に流れるため、人が機器に触れても感電するリスクを低減できます。また、雷撃やその他の異常電圧が発生した際にも、接地システムが過剰な電流を大地に逃がすことで、機器の損傷や火災を防ぎます。特に、コンピュータや制御回路などの非線形負荷を内蔵する電子機器においては、高調波を含む電磁波(EMI)が放出されることがあり、これらの電磁波が金属筐体などに誘導して帯電することを防ぐためにも機能接地が重要です。さらに、接地は回路の基準電位を安定させる役割も持ち、電圧変動の影響を抑制し、電子機器の安定した動作に寄与します。このように、接地は人体の安全確保だけでなく、設備やシステムの信頼性を維持するためにも不可欠な要素です。
接地抵抗の要素
接地抵抗とは、接地極と大地の間の電気的な抵抗を示す値です。この接地抵抗は、主に以下の3つの要素から構成されています。第一に、接地線自体の抵抗と接地極自身の抵抗です。これらは導体であるため、通常は非常に小さい値であり、問題になることはほとんどありません。第二に、接地極の表面とそれに接する土壌との間の接触抵抗が挙げられます。そして第三に、接地極の周囲に広がる土壌そのものが持つ抵抗、すなわち大地抵抗率です。これらの要素のうち、特に接地抵抗値に大きく影響を与えるのが大地抵抗率であり、土壌の種類や水分量、温度、季節によって変動することが知られています。例えば、夏季は土壌の水分量が多いため接地抵抗が低くなる傾向にありますが、冬季は乾燥により高くなることがあります。また、大地抵抗率は金属導体の抵抗率と比較して非常に大きいため、接地抵抗の測定においては、接地極から離れた土壌の影響も考慮に入れる必要があります。
接地抵抗の基準値
接地抵抗には電気設備技術基準によって定められた基準値が存在します。この基準値は接地の種類によって異なり大きくA種B種C種D種の4つに分類されます。これらの種別は主に電気設備の種類や電圧用途によって分けられておりそれぞれに異なる接地抵抗値や電線の仕様が規定されています。例えば一般家庭で使用される電気機器の保護を目的としたD種接地では100Ω以下が基準とされていますが漏電遮断器が設置されている場合は500Ω以下でよいとされています。一方高圧機器の接地や避雷設備などより高い安全性が求められる場合にはA種接地やB種接地が適用されより低い接地抵抗値が要求されます。これらの基準値を満たしていることを確認するために定期的な接地抵抗測定が不可欠です。適切な接地抵抗値を維持することは感電事故や火災の防止機器の故障抑制そして電力系統全体の安定稼働に直結するため非常に重要です。



接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器
接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気
接地抵抗測定の原理
接地抵抗計の測定原理は主に電位降下法に基づいており、接地システムに交流電流を流し、その結果生じる電圧降下を測定することで接地抵抗を算出します。この原理により被測定接地極と大地との間の抵抗値を正確に把握することが可能です。
電位降下法
電位降下法は、接地抵抗測定において一般的に用いられる原理です。この方法では、まず測定対象となる接地極(E)と、そこから十分に離れた位置に補助接地極である電流電極(C)を設置します。次に、接地抵抗計から接地極Eと電流電極Cの間に交流定電流Iを流します。この電流が大地の内部を流れる際に、接地極Eの周囲に電位降下が生じます。この電位降下は、接地極Eからさらに離れた位置に設置したもう一つの補助接地極である電位電極(P)と接地極Eの間の電位差Vとして測定されます。最終的に、オームの法則(R=V/I)に基づいて、測定された電圧Vと流した電流Iから接地抵抗値Rxが算出されます。直流電流を流すと、大地と電極の間に分極作用が生じ、正確な測定が困難になるため、交流電流を用いるのが一般的です。電位電極Pの位置が接地極Eや電流電極Cに近すぎると測定誤差が生じるため、適切な間隔で一直線上に配置することが重要です。
接地抵抗計の構成
接地抵抗計は、接地抵抗を正確に測定するためにいくつかの主要なコンポーネントで構成されています。基本的な構成要素としては、まず本体である接地抵抗計自体があります。この本体には、測定結果を表示するディスプレイや操作ボタン、測定端子などが備わっています。次に、大地に打ち込むための2本の補助接地棒が必要です。これらの補助接地棒は、電位降下法において電流電極(C)と電位電極(P)として機能します。さらに、接地抵抗計と被測定接地体および補助接地棒を接続するための測定コードが3本(通常は緑・黄・赤の色分けがされている)付属しています。これらのコードは、被測定接地極に接続するE端子用、電位電極に接続するP端子用、電流電極に接続するC端子用にそれぞれ対応しています。測定コードは10m、20mと長尺のものが多いため、コードリールがあると便利です。また、簡易測定用の測定プローブが付属している機種もあります。機種によっては、内部抵抗の高い電圧計を使用したり、地電圧の影響を受けにくい交流電位差計方式を採用したりするなど、悪条件下でも正確な測定ができるよう工夫が凝らされています。
補助接地極の設置方法
接地抵抗測定における補助接地極の設置方法は、正確な測定結果を得るために非常に重要です。精密測定(三極法)の場合、測定対象の接地極(E)から約5~10m間隔で、ほぼ一直線上に2本の補助接地棒(P端子用、C端子用)を大地に深く打ち込みます。補助接地棒は、できるだけ湿気の多い土壌に打ち込むのが理想的です。もし乾燥した場所や小石の多い場所、砂地などで打ち込みが困難な場合は、打ち込んだ部分に十分に水をかけて湿らせる、または濡れ雑巾などを補助接地棒の上にかけるといった対策が必要です。コンクリート上では、補助接地棒を寝かせ、水をかけるか濡れ雑巾をかけることで対応します。もし障害物があって一直線上に配置できない場合は、E-P間とE-C間に角度をつけて配置することも可能です。補助接地棒の抵抗値が大きすぎると、正確な測定ができないため、抵抗値が5kΩ以下になるように設置することが望ましいです。測定前には、地電圧が3V以下であることを確認することも重要です。地電圧が高い場合、測定誤差が大きくなる可能性があるため、対象機器の電源を切るなどの対策を講じる必要があります。



接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器
接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気
接地抵抗の測定方法
接地抵抗測定は、電気設備の安全性を確保するために不可欠な作業です。主な測定方法として、精密測定(三極法)と簡易測定(二極法)、そしてクランプ式接地抵抗計を用いた方法があります。それぞれの測定方法には特徴があり、現場の状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。
精密測定(三極法)
精密測定、または三極法は、接地抵抗を最も正確に測定する方法として広く用いられています。この方法では、測定対象の接地極(E)に加え、補助接地極として電流電極(C)と電位電極(P)の2本を大地に打ち込みます。接地抵抗計のE端子には緑、P端子には黄、C端子には赤の測定コードを接続し、それぞれ被測定接地体と補助接地棒に接続します。補助接地棒は、被測定接地極から約5~10m間隔で、ほぼ一直線上に配置することが推奨されており、これにより、接地極周囲の電位分布が安定し、正確な測定が可能となります。測定に先立ち、地電圧(大地に流れる漏洩電流などによる電圧)が3V以下であることを確認することが重要です。地電圧が高い場合、測定値に大きな誤差が生じる可能性があるため、必要に応じて電源を切るなどの対策を講じます。測定は、接地抵抗計のレンジを最大値に設定し、その後、測定値に応じて低いレンジに切り替えて行います。この方法は、A種からD種まですべての種類の接地抵抗を正確に測定できるというメリットがありますが、補助接地棒を打ち込む場所が必要となるため、測定場所が限られる場合があります。
簡易測定(二極法)
簡易測定、または二極法は、補助接地棒を打ち込むことが困難な場所、例えばビルや病院のコンクリート床面などで接地抵抗を測定する際に用いられる方法です。この方法では、測定対象の接地極(E)と、抵抗値が既知でかつ被測定極の抵抗値に比べて十分に低い別の既設接地極(例えば埋設された水道管など)を補助接地極(PまたはC)として利用します。接地抵抗計のE端子を被測定極に、P端子(またはC端子)を既設の補助接地極に接続して測定を行います。この方法で得られる測定値は、被測定極の抵抗値と補助接地極の抵抗値の合計値となるため、被測定極の正確な抵抗値を知るには、補助接地極の抵抗値を事前に把握しておく必要があります。しかし、もしD種接地(100Ω以下)の基準を満たしているかどうかのチェックが目的であれば、合計の測定値が100Ω以下であれば基準を満たしていると判断できます。簡易測定のメリットは、測定が簡単で補助接地棒を打ち込む手間がない点ですが、測定できる接地の種類が限定される(主にD種接地向け)点や、補助接地極の抵抗値が測定誤差に影響を与える可能性がある点がデメリットとして挙げられます。活線での測定は感電の危険があるため、絶対に行わないように注意が必要です。
クランプ式接地抵抗計
クランプ式接地抵抗計は、補助接地極を大地に打ち込む必要がなく、接地線をクランプするだけで接地抵抗を測定できる非常に便利な測定器です。この測定器は、主に多重接地されているシステム(複数の接地極が並列に接続されている場合)の接地抵抗測定に特化しています。測定原理は、接地線に電圧を注入するセンサーと、そこを流れる電流を測定するセンサーの2重コア構造を利用しています。クランプした接地線に一定の電圧を注入し、その際に流れる電流を測定することで、オームの法則(R=V/I)に基づき多重接地ループ全体の抵抗を算出します。多重接地の場合、並列に接続された複数の接地極の合成抵抗が非常に小さくなるという特性を利用しており、接地極の数が増えるほど合成抵抗値はさらに小さくなります。これにより、測定対象の接地抵抗を正確に求めることが可能になります。クランプ式接地抵抗計の大きな利点は、測定作業の簡便さと時間短縮にありますが、単独接地(独立接地)の測定には使用できないため、注意が必要です。特高・高圧機器の外箱や避雷針の接地抵抗測定、通信用接地など、幅広い用途で活用されています。
測定における注意点
接地抵抗測定を行う際には、正確な測定結果と作業の安全を確保するためにいくつかの重要な注意点があります。まず、測定は交流電源を用いて行う必要があります。これは、大地が電解質的な性質を持ち、直流電流を流すと分極作用が生じて正確な抵抗値が得られないためです。また、測定中に地電圧(大地に存在する漏洩電流などによる電圧)が高い場合、測定値に大きな誤差が生じる可能性があるため、地電圧が3V以下であることを確認し、必要であれば対象機器の電源を切るなどの対策を講じます。地電圧が高いことは、電路や負荷機器の絶縁劣化を示唆している場合もあるため、絶縁抵抗試験と併せて保守を行うことが推奨されます。さらに、精密測定(三極法)の場合、電流回路と電圧回路が互いに90度以上の交差角を設けるように電極を配置し、電流回路の電源が接地されている場合は必ず絶縁変圧器を用いて電源回路から絶縁することが求められます。電圧測定には内部抵抗の高いデジタル式電圧計を使用し、電流回路にはできるだけ大きな電流を流すことで、より信頼性の高い測定が可能です。活線での測定は感電の危険があるため、絶対に行わないように注意し、接地抵抗計の測定端子に触れないよう細心の注意を払う必要があります。



接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器
接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気
接地抵抗計の種類と選び方
接地抵抗計は、その測定方式や機能によって多様な種類があります。現場の状況や測定目的、求められる精度に応じて最適な接地抵抗計を選ぶことが、正確な測定と効率的な作業を実現する上で重要となります。
接地抵抗計の種類
接地抵抗計は、測定方法や表示方式によっていくつかの種類に分類されます。主な種類としては、精密測定(三極法)に対応した機種、簡易測定(二極法)に特化した機種、そして補助接地極が不要なクランプ式接地抵抗計があります。表示方式では、測定値を針(指針)で示すアナログ表示式と、数値で表示するデジタル表示式が存在します。アナログ式は直感的に抵抗値の傾向を把握しやすい一方、デジタル式は数値を正確に読み取ることが可能です。また、ダイヤルを回して検流計の針がゼロを指すように調整し、その時のダイヤル目盛を読むタイプの接地抵抗計も存在します。これらの基本的な測定方式や表示方式に加えて、近年ではBluetooth通信機能を搭載し、測定値をスマートフォンやタブレットに転送できる高機能なモデルも登場しています。さらに、絶縁抵抗測定機能と接地抵抗測定機能を兼ね備えた複合型の計測器や、活線警告機能、ノイズチェック機能、メモリー機能など、様々な付加機能を備えた製品が開発されており、多様な現場のニーズに対応しています。
様々な接地抵抗計の特長
接地抵抗計には、その種類に応じて様々な特長があります。精密測定(三極法)に対応した接地抵抗計は、A種からD種までの幅広い接地工事の抵抗値を正確に測定できる点が最大の特長です。特に高圧機器や避雷設備の接地など、厳密な測定が求められる場合に適しています。多くの機種で地電圧測定機能が搭載されており、測定誤差の原因となる地電圧の影響を確認できます。また、補助接地抵抗が大きくても正確な測定が可能な耐ノイズ性能に優れたモデルも存在します。簡易測定(二極法)に特化した接地抵抗計は、補助接地棒を打ち込むのが難しい環境でのD種接地測定に非常に有効です。小型で操作が簡単なものが多く、活線警告機能やAC/DC電圧測定機能を備えている製品もあります。微小測定電流で漏電ブレーカーの動作を防ぐ設計の機種も存在し、手軽にD種接地を確認したい場合に便利です。クランプ式接地抵抗計は、補助接地極が不要で、接地線をクランプするだけで測定できる手軽さが最大の魅力です。多重接地されたシステムにおいて、短時間で接地抵抗や漏れ電流を測定できるため、作業効率を大幅に向上させます。バックライト機能で薄暗い現場でも測定値を確認しやすく、データ保存機能を備えたモデルも多くあります。しかし、単独接地は測定できないという制約があります。これらの接地抵抗計の使い方は、機種によって異なりますが、一般的には、測定端子を接地極と接地線に接続し、スイッチをオンにして測定値を確認するという流れになります。適切な接地抵抗計の選定と正しい使い方は、電気設備の安全確保と効率的な保守作業に直結します。



接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana![]()
![]()
![]()
BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気計器
接地抵抗計(アーステスター)|BuhinDana BuhinDana では三和電気計器・日置電機・共立電気